オカルトは全て説明が可能
変わったところに打球が飛ぶ、ピンチの後にチャンスあり、先頭打者に四球を出すのは流れが悪い。
統合失調症レベルのオカルトが世の中にはびこっているが、こんなのは全て説明がつく。
変わったところに打球が飛びやすいわけがない
まず、変わったところに打球が飛ぶだが、これは完全に印象でしかなく全く根拠がない。
それでも、誤差程度に打球が飛ぶ傾向にあるとするのであれば、打球が飛びやすい条件が整っていたから守備を変えたということが考えられる。
守備交代したから打球が飛ぶのではなく、その方向に打球が飛んできそうだから予め変えるのであって因果関係が逆なのだ。
あるいは守備交代をする前の選手は守備力に劣るということになるので、バッテリーからすれば極力そこら辺には打たせたくないという意識が働く。
それが、守備交代をしたことで不安要素がなくなったので、今までとは違ってそこに打たせても良くなるため配球も変わる。
むしろ、今までしてなかった攻めをすることができるので、結果的に変わったところに打球が飛びやすい配球になるのかも知れない。
守備範囲が変わることから、交代前の選手であれば追いつけなかった打球が交代後の選手なら追いついてしまうことから、結果的には変わったところに打球が飛んだように見える現象が発生することもあるだろう。
本当に変わったところに打球が飛ぶようなことがあったとしても、何かしらの理由があるわけで超常現象によって発生しているわけではない。
この場合守備が下手な選手から上手い選手に変わったケースを挙げたが、故障などによって下手な選手に切り替わった場合は、相手選手が守備の穴となるところを狙って来ることが考えられるので、やはり理由があって打球が飛ぶことを説明できる。
ピンチの後はチャンスになりやすい
ピンチの後にチャンスありこれもよく言われることだが、根拠がなくありえない話である。
これが事実だとすれば、毎回ピンチになっている弱小チームほどチャンスの機会に恵まれるわけだから、さぞかし毎試合スリリングな展開になって見ごたえがあるだろうね。
そんな事があるわけもないので、ピンチの後にチャンスありは否定できるのだが、それでも可能性を主張するなら、ピンチを切り抜けたチームの方が展開的に有利な状況になっているのだから、精神的な面ではチャンスを得やすいであろう。
ピンチを脱したということは、相手からすればチャンスを逃したということで、当然気分は良くない。
勝てるチャンスを逃した方は、これで負けるようなことがあれば余計にショックが大きいため、絶対に負けられないという意思が働き、焦りや気負いが生じる。
対して本来であれば負けが濃厚だった側が運良く悪い局面を打開できれば、気持ちに余裕ができるので精神面や展開面で優位に立てる。
結果として自分は普段通りの力を出すことができるのに対して、相手は余計な気負いから実力を発揮できないことで、チャンスを生み出しやすい下地ができるということになる。
まかり間違ってもピンチの後の攻撃は正面の平凡なゴロがイレギュラーをしやすくなって、チャンスが生まれやすいなんてことはありえない話である。
先頭打者に四球を出すのはそもそも調子が悪い証拠
先頭打者に四球を出すと流れが悪くなると言うが、四球だろうがなんだろうがノーアウトのランナーを出す時点で不利なことには変わらないわけで、流れが悪くなるというのは当たり前のことだ。
ストライクが入らないなら言うまでもなく、球を見られているということも球威がないと予測がつく。
四球を出したから流れが悪くなるのではなく、調子が悪いから流れが悪くなるのであって、これも因果関係が逆であると言えるだろう。
ヒットなら良いとする話はあるが、ヒットを打たれるか打たれないかは偶然によるところも多いだけに、調子と関係なしにヒットを打たれてしまった可能性があるので、ヒットよりも四球の方が悪いかも知れないという話だと考えられる。
しかし、打たれているのは事実なので単純に調子が悪くて打たれているのであれば、むしろヒットを打たれている方がより状態は悪いのではないだろうか。
ほとんどのオカルトは単なる偶然でしかなく、理由を考えることすら馬鹿らしいものばかりである。
それでもあえて説明をするのであれば、いくらでも理由は考えられるから、そこで何か超自然現象的なことが起きているということだけは絶対にないのだ。
こんな簡単なことを理解できないのだから、スポーツをする連中は体を鍛えるよりも、頭をもう少し鍛えたほうが良いのではないかなと思うのだが。
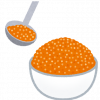





ディスカッション
コメント一覧
全国の野球解説者に戦線布告ですね!
野球解説者は馬鹿にされてることもわからないですよ。
皮肉が通じないのも辛いですね。
ピンチの後にはチャンス論については、結局そのチャンスをつかめない→決定機の損失→決めきれずに負ける→悪いイメージの刷り込みというのはあるかなと。
なんとなく日本独自の理論のような気もするが、本場やほかのスポーツだとどういうことがあるのかも含まれるとより考察として楽しくなりますね。
あれ?海外からのスパムコメントが来てる。
一応、バスケットの話になりますが、アメリカでも選手や監督は流れがあると思っているようで勉強もせずに体ばかり動かしている脳筋は変な幻想にとらわれやすいようです。
ちなみにここで流れがないことは証明されています。