開門場所を決めるのにサイコロ振る意味ありますか
手積みならまだしも何が積まれているかわからない全自動宅で、サイコロ振る意味ってある?
こんなの無駄以外の何物でもないし、余計なことをすれば取り間違いの問題が起きるだけだからなくしたほうが良い。
取り出し位置を間違ったところで大きなペナルティもなくそのまま続行をするんだから、最初からサイコロなど振らずに所定の位置から取るようにしておけばいいだけの話だ。
取り出し場所はどこでも良いのだが、親の牌山の右端かあるいは8トン目が良いだろうね。
王牌があるのが常に北家か東家ってことにしておけば、誰が親だか間違うこともなくなり、自風を勘違いするということも減るだろう。
もっとも、こんな勘違いはめったにあることではないが、少しでもその可能性を減らすことができるのであれば取り出し位置は固定のほうが優秀だ。
サイコロを振るという行為はイカサマが前提にある話だから、プロの対局とかで振っているのをみるとあんたらイカサマでもするんですかってことになる。
プロの走りが雀ゴロ集団で、イカサマでしのいでいた連中がプロになったという流れがあるからサイコロも残ってるのかも知れないが、クリーンなイメージにしたいのであればますますサイコロをなくすべきだ。
自動配牌卓だとサイコロの目と取り出し位置が一致していないようなので、飾りあるいは自動配牌にしない時ようにサイコロがあるだけっぽいので、無駄が排除されているように見えるのだが気になる点がひとつ。
王牌の位置がランダムっぽい雰囲気なのが気になる。どうやらサイコロの目とは関係なくランダムの位置から配牌を取り出しているような感じ。
こんな中途半端なことにするならサイの目に合わせれば良いし、そうしないのであればでてくる山は位置を固定したほうが良い。
自動配牌卓は親が第一ツモを取得しないと行けないっぽいので、スムーズに進行できるように右6辺りから取り始める形にでもすればいいのに。(右6の考え方自体サイコロありきではあるが、まだまだ多数いるサイコロ派のために違和感のない位置から始めるのは悪くないだろう)
九種九牌や四家立直、四風子連打や四槓流れの途中流局は合理性がないと排除されていく一方で、全く意味をなさない配牌の取得が簡素化されないのが謎である。
途中流局は流局になる合理的な理由がないにしても選択肢が広がる分だけ、ゲーム性がわずかに増すかも知れないが、配牌の取り方なんてゲームに何の影響もないのだから、一番わかりやすく合理的な形にするべき部分ではないだろうか。
手積みであれば悪意の有無を問わず見えてしまった牌を自分の有利になるように、積みかねないだけにサイコロを振る意味もあるが、全自動が当たり前の時代ではお飾りにしか過ぎない。
もっと言ってしまえば、牌山を積むこと自体あってもなくても良いはずなんだけどね。


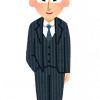


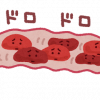
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません